2025年03月17日
ROMとRAM (1)
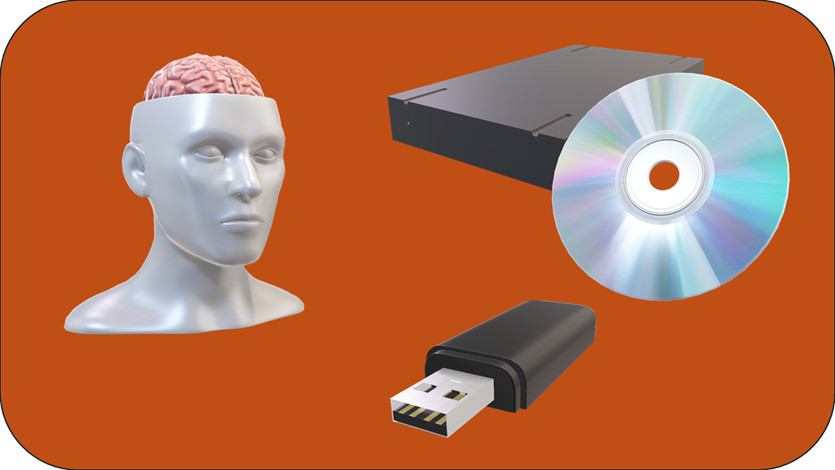 突然ですが、皆様の記憶力はいかがでしょうか?
突然ですが、皆様の記憶力はいかがでしょうか?
今まで使っていた工具がない(きっと、妖怪物隠し?)など、直近の記憶を行う短期記憶。
一方、人の名前や、日常単語など、いわゆる頭で長い間記憶する長期記憶があります。
両方とも重要で、加齢とともに衰えていくものらしいです。
さて、ITの世界では、記憶装置につきまして、分類方法として、機能的分類と、特性的分類の主に2つが存在します。
機能的分類としては「主記憶装置」と「補助記憶装置」。
特性的分類としては「ROM」と「RAM」。
それぞれを採り上げていきましょう。
機能的分類である「主記憶装置」と「補助記憶装置」。
記憶装置といえば、主記憶装置を指すことが多いです。
パソコンなどのスペックシートでは、「メモリ」「メインメモリ」とも書かれていることが多いです。
主記憶装置の主な役目は、そのシステム内での情報を記憶していくことです。
アドレスを指定し、演算結果などを書込・読込を行い、システムを動かしています。
アプリ屋さんの頭痛の種、ポインタとメモリアクセス違反は、この装置によって引き起こされます。
エラーに関しては、OS側でメモリの利用状況から出されるもので、システムの保護に役立ちます。
とはいえ、プログラミングデバッグ中での厄介さは、相当なトラウマになりますが・・・
一方、補助記憶装置は、主記憶装置の不足部分を補ったり(メモリのページング)、
ファイルストレージとして電源が切れたあとも、データを保存することができます(データセーブ)
一般論ではありますが、
主記憶装置は高速だが、容量が小さい。揮発性で、常に電源供給が必要。
補助記憶装置は低速だが、容量が大きい。不揮発性で、電源供給がされなくでもデータは保存される。
というのがあります。
現在のメインメモリが8〜32GBを基準値だと考えると、ファイルストレージ(ハードディスクやSSD)は256GB〜8TBと、その差は歴然としていることが理解できるでしょう。
冒頭の長期記憶、短期記憶を当てはめますと、
主記憶装置は短期記憶、補助記憶装置は長期記憶として利用することが大半となります。
次はROMとRAMに関して紹介します。
ROMは「Read Only Memory(読み込み専用)」の記憶装置になります。
DVD-ROMや、パッケージ化されたゲームソフト(特に古い)がメインに挙げられるでしょう。
また、アプリ屋さんにはなじみの薄い、コンピュータをOSよりも下層で制御する「BIOS(バイオス:Basic Input Output System)」などにも利用されています。
簡潔に述べてしまえば、同じデータを使い続けるときに利用する部品ともいえるでしょう。
ここで1点、小さな嘘が書かれているのですが、それは次回に紹介したいと思います。
一方のRAMは「Randum Access Memory」の略です。
メモリ上の番地を指定して、データの読み書きを行える方式です。
PC上の主記憶装置、ビデオボードのRAM、USBフラッシュメモリなどが、それに該当いたします。
多くのシステムでは、特にパソコン系のシステムでは、ROM / RAMの両方で車輪の軸となります。
次回は、今回を踏めて、マイコンボードでのROMとRAMを中心に記事にしたいと思います。
IoT開発を行って、仕事の効率化や豊かな生活を送りませんか?
「Let's extend technology!!」
を合言葉に、
IoTの事例やヒント、開発記を投稿していきます!
ハードウェア業者と、話がうまくできない。
そんなときは、両方に対応している弊社にご相談ください。
お待ちしております!



